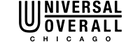WORKERS STYLE vol.15
ヘリテージパンツは完成していない。
ワークウェアとは、現場で履かれて働いて、初めてワークウェアとしての本来の意味・価値が伴う。着る人が自分の癖や働き方、思想を反映させるためのツールのような存在。ワーカーが自分の働くスタイルに合わせてカスタマイズし、それぞれのライフスタイルや価値観を表現していくアイテム。着る人の使い方やこだわりによって、ワークウェアは初めて「完成」されていく。このパンツがどんな風にその人にとっての欠かせない自己表現になるのか。ヘリテージパンツを通して、様々なワーカーにスポットをあてていく。

Kazu Tsunashima / サインライター
1995年生まれ。千葉県出身。大学卒業後、新卒で広告会社に就職し2年間勤めた後、1年間の期間を経てイギリスへ渡る。現地でサインライターの元で2年間の修行を経て独立し、現在も手書き文字による看板や空間演出を中心に活動。手を動かすこと、街の表情をつくること。書くことを通して、街と人との新たな関係性を描いている。

―― 今日はお忙しい中お時間ありがとうございます。
綱島:いえいえ、こちらこそ遠いところありがとうございます。
―― もうすっかり夏ですね。この辺は地元を思い出します。
綱島:いいですよね、この辺。村って感じで。梨農家が多いんですよ。

―― 駅から歩いてきたので拝見しました。空気がおいしくて最高でした。では早速ですけど、インタビュー始めます。お名前からお願いします。
綱島:綱島一洋です。東京出身で、今はサインライターという肩書きで活動しています。年齢は29歳です。
―― サインライターという職業、まだ聞き慣れない方も多いかもしれませんね。
綱島:そうですね。ざっくり言えば“手描きの文字を書く人”ですね。建物の壁にお店のロゴを描いたり、ガラスにペイントしたり、メニューや案内のサインだったり。素材も木や金属、布とか様々です。

―― どんなキャリアからこの仕事に辿り着いたんですか?
綱島:大学を出て、最初は広告会社に入社しました。2年働いたんですが、会社を辞めてから1年間はアルバイトをしながら、自分のやりたいことを探していました。その流れでイギリスに行って、サインペイントに出会いました。

―― イギリスって、今でも手描き文化が根強く残ってるんですよね。
綱島:そうなんです。現地の人は「これはサインライターの仕事だよ」って普通に言うんですよ。それがめちゃくちゃかっこよくて。こんな風に職業として成立しているんだって衝撃でした。

―― どうやって現地で技術を学んだんですか?
綱島:独学というより、現場に飛び込む感じです。気になるサインを見つけたら「これ誰が描いたんだろう?」って直接聞いて、その人に会いに行って、「手伝わせてください」って頼んで。一緒に現場に行って、最初は道具渡すだけだったけど、少しずつ描かせてもらえるようになりました。

―― すごいですね。日本に戻ってからはすぐに独立されたんですか?
綱島:はい。イギリスではビザの関係でサインライターとして滞在し続けるのが難しくて、帰国後はそのまま個人で活動しています。
―― では、ちょっと服の話に移ります。今日履いていただいたヘリテージパンツ、どうでしたか?
綱島:めちゃくちゃちょうどいいです(笑)。午前中も現場で作業してたんですけど、しゃがんだり登ったりが多いので、ピタッとしすぎてるとしんどい。でもこれは動きやすいし、ラクですね。

―― 作業着を選ぶ時って、どういうところを重視されてますか?
綱島:動きやすさと、汚れても気にならないかどうかです。道具として信頼できるかっていうのが重要ですね。服も、刷毛やペンキと一緒で“ツール”なんです。

―― “ツールとしての服”。かっこいいですね。
綱島:いやいや(笑)。でも本当にそれぐらいの距離感で捉えてます。ファッションってよりは、作業に集中できるかどうか。
―― サインを書く上で大切にしていることって何でしょうか?
綱島:“線を残す”ことです。誰が描いても似てるようで、線ってその人の癖が出るんですよ。積み重ねるうちに、「これ、自分の線だな」って思えるようになる。それを探してる感じですかね。

―― まさにその積み重ねが綱島さんの線になるわけですね。
綱島:なんか恥ずかしいですね(笑)
――今後はそんな線を積み重ねていくことで今後何か目標などありますか?
綱島:でかい目標とかはあんまり考えてないです。今、目の前の仕事をちゃんとやって、頼んでくれた人にちゃんと応える。それを一つずつ積み重ねていければ、それで十分かなと。

ペンキの飛沫、膝の皺、それも含めて「線」なのだと、綱島一洋の言葉は教えてくれる。
看板に残す文字は、街の記憶に溶け込みながら、確かに誰かの視界に引っかかる。
描くというより、残す。サインとは、空間のどこかに静かに線を刻む仕事だ。
そしてヘリテージパンツは、彼のそんな日々に寄り添う。
汚れていくことも、しゃがむ動作も、絵の具の跡も――すべてが「自分の線」になっていく。
作業着としての服が持つ本当の意味を、彼は何も飾らず、まっすぐに教えてくれる。

text and photograph hilomi