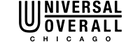WORKERS STYLE vol.15
ヘリテージパンツは完成していない。
ワークウェアとは、現場で履かれて働いて、初めてワークウェアとしての本来の意味・価値が伴う。着る人が自分の癖や働き方、思想を反映させるためのツールのような存在。ワーカーが自分の働くスタイルに合わせてカスタマイズし、それぞれのライフスタイルや価値観を表現していくアイテム。着る人の使い方やこだわりによって、ワークウェアは初めて「完成」されていく。このパンツがどんな風にその人にとっての欠かせない自己表現になるのか。ヘリテージパンツを通して、様々なワーカーにスポットをあてていく。

Kazu Tsunashima / サインライター
1995年生まれ。千葉県出身。大学卒業後、新卒で広告会社に就職し2年間勤めた後、1年間の期間を経てイギリスへ渡る。現地でサインライターの元で2年間の修行を経て独立し、現在も手書き文字による看板や空間演出を中心に活動。手を動かすこと、街の表情をつくること。書くことを通して、街と人との新たな関係性を描いている。

―― 今日はお忙しい中お時間ありがとうございます。
綱島:いえいえ、こちらこそ遠いところありがとうございます。
―― もうすっかり夏ですね。この辺は地元を思い出します。
綱島:いいですよね、この辺。村って感じで。梨農家が多いんですよ。

―― 駅から歩いてきたので拝見しました。空気がおいしくて最高でした。では早速ですけど、インタビュー始めます。お名前からお願いします。
綱島:綱島一裕です。今は“サインライター”という肩書きで活動しています。いわゆる「手描きの文字を書く人」です。看板や室内のサイン、メニューなど。描く場所も壁だったりガラスだったり、素材もさまざまです。

―― 元々は広告会社にいたと伺いました。
綱島:はい。大学を卒業して広告会社に入って、2年間勤めました。その後1年間、自分が本当にやりたいことを模索して、思い切ってイギリスに行ったんです。

―― サインライターとしての修行は、現地で?
綱島:そうです。最初はSNSで見つけて、DMを送って。現場に同行させてもらって、最初は道具を渡すところから始めました。少しずつ手を動かさせてもらうようになって……その積み重ねですね。

―― 実際、どんな現場が印象に残っていますか?
綱島:チェルシーのスタジアムの仕事です。現場の大きさも暑さも尋常じゃなくて(笑)。終わった時に疲労と解放で泣いてしまったのを覚えています。あと、ロンドンで師匠と一緒にハウスナンバーを書いたとき、クライアントの方が泣いていて。それを見て自分ももらい泣きしてしまって。文字って、こんなに人の感情に響くんだって思いましたね。

―― そういう経験が、今の綱島さんのスタイルに繋がっていると。
綱島:はい。自分の作品を見たクライアントさんから「もともとこういう看板があったみたい」「らしい文字ですね」って言っていただけることがあって。すごくうれしい言葉です。目立つことよりも、その土地やお店、人に馴染むことを大切にしているので、そう言われたときは「ちゃんと届いたな」と思えます。

―― 線についてのこだわりも強く感じます。
綱島:線って、その人の癖が出るんですよね。誰が描いても似ているようでいて、ちょっとずつ違う。だから、“線を残す”ことが大事。自分でもまだ途中ですが、「これは自分の線だな」と思える瞬間が少しずつ増えてきました。

―― 道具選びにもこだわりがあるんですか?
綱島:あります。イギリスで使っていた筆に慣れているので、今も基本的にはそれを使っています。素材や表面によって、塗料や筆を使い分けて提案しています。ガラス一枚でも、内側から描くか外側から描くか、お店の雰囲気によって最適な方法は変わってきますから。

―― 祖父の存在も影響を与えていると聞きました。
綱島:そうですね。祖父は梨農家だったんです。一人で家の庭も畑も全部やっていて。ものづくりへの姿勢、家族への思い。それが自分の根底にある気がします。
―― 少し服の話に移らせてください。今日履いていただいたヘリテージパンツの印象は?
綱島:めちゃくちゃちょうどよかったです(笑)。しゃがんだり登ったり、作業が多いので、動きやすくて助かってます。汚れを気にせず動けるのもいい。作業着って“構えない”のが大事なんですよね。

―― 作業着は道具の一部だと?
綱島:まさに。筆や塗料と一緒です。動きの中にフィットして、自分を支えてくれる。道具として信頼できるかどうか。だから服もツールなんです。
―― 最後に、これからの目標があれば教えてください。
綱島:大きな目標というよりは、今目の前にある依頼に丁寧に応えること。クライアントの想いや空間にフィットする文字を描いていく。それを一つずつ積み重ねることが、自分の“線”になるんじゃないかと思っています。

綱島さんの「線」は、まっすぐで、静かだ。
看板に残る文字は、ただの情報伝達ではない。
それは空間に沁み込み、街の風景と人の記憶に残っていく。
“道具としての服”と彼が語ったヘリテージパンツ。
汚れても、しゃがんでも、絵の具が跳ねてもいい。
すべてが「線」になる。彼の仕事がそうであるように。
手描きの線には、温度がある。
描くというより、残していくなのか。
今日も彼は街のどこかに、新しい線を静かに刻んでいる。

おまけ。

かわいい。
text & photograph : hilomi